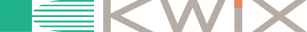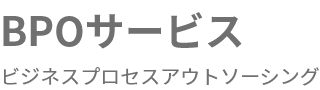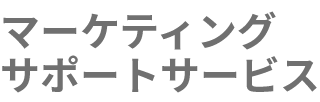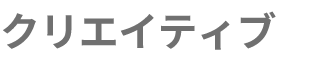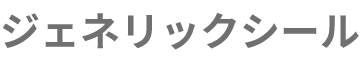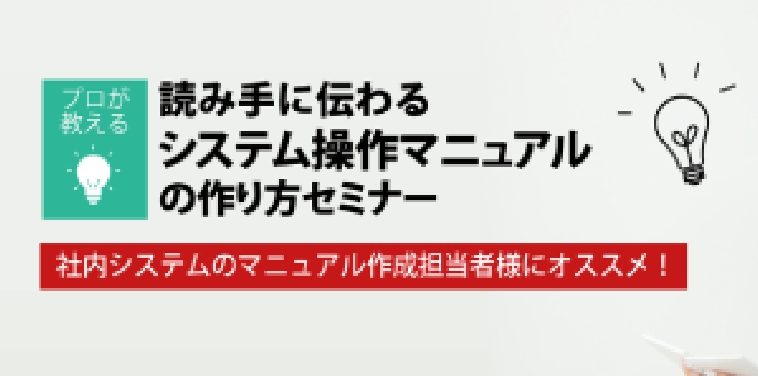コラム Column
マニュアル
2025-10-24
【システム開発メーカー向け】基幹システムリプレース時のマニュアルづくり~問い合わせを減らし、信頼を守るために~
リプレース後の問い合わせ増加――。 その原因、マニュアルにあるかもしれません。

システムをリプレースした直後、「操作がわからない」「前の方が使いやすかった」といった問い合わせが増えることは珍しくありません。
多くの現場では開発スケジュールを優先するあまり、マニュアル整備が後回しになりがちです。
しかし、導入後に問い合わせ対応が膨らめば、サポート工数の増加や顧客満足度(CS)の低下につながります。
本コラムでは、マニュアル担当者の視点から、リプレースを円滑に進めるためのマニュアル設計と運用のポイントを解説します。
リプレース後に起こる“想定外”の問い合わせ
システムをリプレースすると、画面構成や操作手順の変化によりユーザーが戸惑う場面が必ず発生します。
たとえば「請求データの登録方法が見つからない」「ボタンが消えた」「レポートが出力できない」といった問い合わせが続出することも。
こうした混乱の多くは、システムそのものではなく、「マニュアルが更新されていない」「変更点が伝わっていない」ことが原因かもしれません。
マニュアルは“ユーザーの混乱を防ぐツール”であり、“企業のサポート負担を抑える仕組み”でもあります。
「リプレースだからこそ」必要な説明とは
リプレース後の操作マニュアルに求められるのは、「何をどう変えたか」を明確に伝えることです。
単に新しい手順を載せるだけでなく、旧システムとの違いを整理して示すことがポイントです。
- 操作の変更点を比較で示す(例:旧画面との対比表)
- 変更の理由を補足する(例:「処理を安全化するため」など)
- 問い合わせの多い操作を先頭に配置する
- エラー時の対処法を具体的に記載する
こうした工夫により、利用者の理解を深め、問い合わせの大半を未然に防ぐことができます。
マニュアルはリリース準備の一部と捉える
リプレースでは、仕様変更やUI調整が繰り返されるため、マニュアルを後回しにすると整合性が崩れやすくなります。
「完成したらマニュアルを書く」ではなく、設計段階から並行して構成案を作ることが成功の鍵です。
要件定義の段階で、
- ユーザーが迷いそうな操作
- 用語の統一方針
を明確にしておくと、開発とマニュアルの両面で整合性を取りやすくなります。
また、開発チームとマニュアル担当者が連携する体制を早期に築いておくことで、システム変更に追従した更新がスムーズに進みます。
クイックスでは、こうした開発チームとの並行作業にも対応したマニュアル構築支援を行っています。
継続的な更新ルールを整える
マニュアル整備で最も多い失敗は、「リリース後に放置される」ことです。
更新担当者が不明確なまま時間が経過すると、古い情報が残り、誤操作や再問い合わせを招く原因になります。
リプレース後は、次のような運用ルールを明確にしましょう。
- 改訂内容を管理する台帳を用意し、更新履歴を残す
- 変更時にはユーザー向けに「更新通知」を出す
- よく閲覧されるページや問い合わせ内容を分析し、改善に反映する
マニュアルを“作って終わり”ではなく、“育てる仕組み”に変えることで、問い合わせ対応の負担を抑え、顧客からの信頼を維持できます。
"使われ、育つマニュアル"の条件
どれだけ丁寧に作っても、使われなければ意味がありません。
操作マニュアルを「読まれるもの」から「すぐ参照できるもの」に変える工夫が必要です。
WordやPDFマニュアルは手軽に作成できますが、更新や検索が煩雑になりがちです。
最近では、Webマニュアル(HTMLマニュアル)への移行が進んでいます。
Webマニュアルの主なメリットは以下の通りです。
- 検索ボックスで必要な操作をすぐ探せる
- 用語リンクや動画で補足説明を追加できる
- 修正が即時反映され、常に最新版を維持できる
リプレース後の運用負荷軽減や、問い合わせ削減の観点でも効果的な手法です。
もしまだ本格的なマニュアルのWeb化に取り組んでいない場合は、今後の選択肢として検討してみるのもよいでしょう。
まとめ
システムリプレースは、技術的な刷新だけでなく、利用者への理解をつなぐ橋渡しでもあります。
操作マニュアルを軽視すると、問い合わせ対応が膨らみ、結果的にプロジェクト全体の効率を下げかねません。
一方、設計段階からマニュアル制作を組み込み、変更点をわかりやすく伝えることで「ユーザー定着」と「サポート効率」を両立できます。
クイックスは、よくある課題(変更点が伝わらない/検索しづらい/更新が回らない)に対し、企画・制作~HTML化~運用改善までを一気通貫で支援します。
リプレース後の問い合わせ削減や運用の仕組み化を目指す企業様に、役に立つマニュアルづくりの具体策をご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。