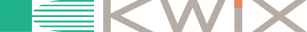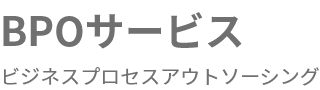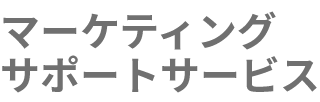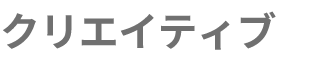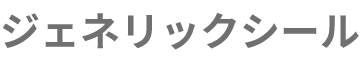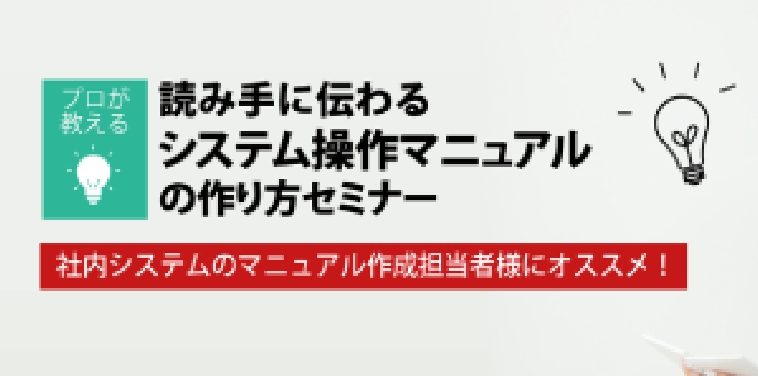コラム Column
マニュアル
2025-07-24
CSも収益も、“伝え方”で変わる? 新サービスを現場に届ける「説明の仕組み」づくり
従業員や顧客へ「どう伝えるか」があいまいなまま、現場に任せきりになっていませんか?

こんな悩み、ありませんか?
- 説明が担当者ごとにバラバラで、「Aさんの言い方」と「Bさんの言い方」で現場が混乱する
- 新サービスの要点が伝わっていないため、スタッフ同士で「どう説明すればいいか」を再確認し合う毎日
- 浸透までに時間がかかりすぎるせいで、せっかくの新施策がスピード感を失いがち
- OJTだけに任せると、ベテランが不在のタイミングで教育がストップしてしまう
こうした状況は、教育が“設計されていないまま”現場に委ねられているサインかもしれません。
本稿では、ディーラーのアフターセールス部門を起点に、他業界にも応用可能な「教育設計」の重要性と、その具体的な仕組みづくりを紹介します。
OJT依存が招く現場の“バラつき”
新しいサービスや施策を導入したとき、「現場にうまく伝わらない」「サービスアドバイザーの理解が浅い」といった声がアフターセールス部門から上がることは珍しくありません。特に店舗やスタッフの数が多いディーラー組織においては、伝達スピードや内容のバラつきが顕著に表れます。
その背景には、OJT(現場教育)に依存した属人的な教育スタイルがあります。日々の業務の中で都度説明していくOJTは即応性が高い反面、指導者によって内容の深さや説明の仕方に差が出やすく、新サービスのように“最初の理解”が重要なテーマには不向きな場合もあります。
顧客満足度を左右する“伝え方”の質
現場内での理解や説明にバラつきがあると、 顧客満足度(CS)にも悪影響を及ぼします。
新サービスを正しく説明できなければ、顧客の不安や不満を招き、ひいては企業への信頼感を損ねる可能性もあるのです。
CSを高めるうえで、作業品質だけでなく「どう説明されるか」がますます重視されるようになっています。近年の調査でも、リコール対応で来店した顧客の満足度が通常より大きく下がる傾向があり、その要因のひとつとして「一方的な説明」「質問への曖昧な対応」が挙げられています。
これらはすべて、スタッフ個々の“説明のバラつき”によって引き起こされている可能性があります。つまり、現場での説明内容や伝え方を標準化することが、CSを安定させる鍵になります。例えば動画やスクリプトを活用すれば、誰が対応しても一定品質の説明を実現できます。
提案の仕方が収益に直結する構造
アフターセールス部門のもう一つの重要指標が「収益性」です。整備工場においては、車検による収益が全体の6割以上を占め、その中でも現場スタッフが直接影響を与えられるのは「台あたり粗利」です。
台あたり粗利は、主に追加整備の提案によって変動します。その中でも「どれだけ提案できるか(提案数)」と「どれだけ受注につながるか(受注率)」は、教育によって確実に改善できる要素です。つまり、説明の質がそのまま売上に直結するという構造です。
クイックスが支援する「伝わる教育の仕組みづくり」
新しいサービスや施策を現場に定着させるには、「どう伝えるか」の設計が欠かせません。クイックスでは、アフターセールス部門の皆さまが、現場スタッフに的確かつ効率的に伝達できるよう、教育や運用支援を行っています。
「伝える」ための仕組みの運用支援
点検・整備内容などを動画でわかりやすく伝えるための仕組み(取り組む内容の整理、伝達手段、スクリプトとの連携)を設計・支援。顧客とのコミュニケーション改善にもつながります。


トレーニング資料(スライド)の作成支援
新サービスの背景や目的、接客時のポイントをまとめたスライド資料を作成。研修や社内説明会などですぐに活用できます。
撮影用トークスクリプトの設計
整備スタッフやサービスアドバイザーが説明する際の“話し方”や“構成”を標準化。現場の表現に統一感をもたせます。
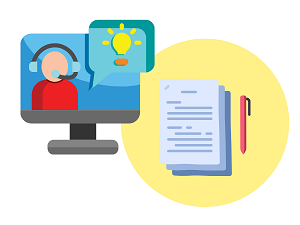
社内教育の整備や、現場への伝え方に課題を感じている方へ
「OJTだけでは不安が残る」「説明の仕方が人によってバラバラ」など、現場教育や情報伝達にお悩みの方はぜひご相談ください。
本コラムで紹介した手法や考え方は、教育の属人化や伝達品質のバラつきに課題を抱える他業界の現場教育にも応用が可能です。
トレーニング資料やスクリプトの整備など、貴社の業務に即した形で支援いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。