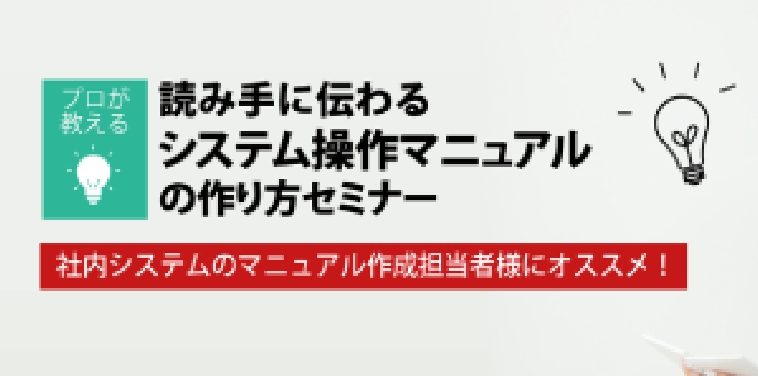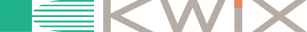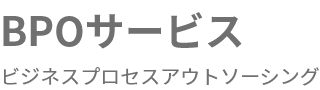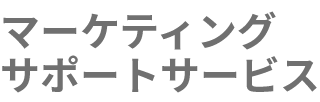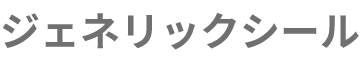コラム Column
マニュアル
2021-02-19
読み手に伝わる業務マニュアルとは
「何故、業務マニュアルが読まれないのか」「どうして業務マニュアルを活用できないのか」と思ったことはありませんか?それは一言で表すと「読みづらい」からです。しかし、ただ見栄えよくすれば読みやすくなるわけではありません。本稿では業務マニュアルの改善が求められる背景や課題、改善のヒントをご紹介します。

「見て覚える」が通用しない時代に!企業を成長させる業務マニュアル
働き方改革関連法が施行され、規模の大小問わずあらゆる企業で残業抑制や、それに伴う生産性向上が強く求められるようになりました。少子高齢化で生産労働人口が減少する一方、限られた人員でこれまで以上の生産性を確保するため、ベテラン社員のノウハウを継承しつつ、人材の流動化に対応する新しい労働環境づくりが模索されています。特に中小企業は事業継続の視点から業務の属人化を是正し、全体最適化を図ることが経営課題として突き付けられています。
一昔前であれば、仕事は「見て覚える」という教わる側の能動的な姿勢が問われていましたが、今は優秀な人材を確保、育成するためにも、教える側がはっきりと業務内容を言語化し、伝えていく必要があります。さらに2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で先輩たちに同行して仕事を教わったり、職場内で働く姿を見て覚えるといったことが難しくなっていることからも、業務内容を言語化して伝えていかなければなりません。
良品計画が運営する無印良品の店舗業務マニュアル「MUJIGRAM」や本社業務マニュアル「業務基準書」に代表されるように、オリエンタルランド、トヨタ自動車、日立製作所、ファーストリテイリング、マクドナルドなどの大手企業で業務マニュアルの改善を企業の成長に結びつけている事例は少なくありません。
業務マニュアルの改善は利用者目線で見ると、業務で分からないことがあった時にすぐアクセスできると、理解度も上がり一人ひとりの自立性が高まります。また、部署異動があっても素早く新しい業務をスタートできるようにもなります。管理者からすれば、社内教育が安定し、定着率も向上します。働き方改革に合わせたジョブローテーションや多能工にも対応します。結果として、品質、CS、生産性が向上し、残業抑制や労働安全の確保につながっていきます。経営的な視点からすると、利用者、管理者の業務効率化により、利益率が向上し、事業継続が展望できるようになることは言うまでもありません。先ほど挙げた業務マニュアルを改善した企業はその重要性をしっかりと理解していると言えます。
「読みづらい」を解消する伝わる5つの条件
業務マニュアルを改善する前段として、現行のマニュアルの課題を把握することが必要です。弊社が実施したアンケート調査によると、業務マニュアルの課題で一番に挙がるのは「読みづらさ」です。
何故、多くの業務マニュアルは「読みづらい」のでしょうか。一番に考えられるのは制作上の課題です。担当者が前任者に正しい手順、要領を伝える書き方を教わっていなかったり、複数の作成者間で書式も構成もばらばらで統一感がないと読みづらいマニュアルになってしまいます。せっかく持っているマニュアルも管理方法が悪いとそれも使いにくいものになります。最新版がどのファイルか分からない、見たい時にすぐ見られない、欲しい情報がどこにあるのか分かりにくいといったことが、業務効率を大きく損ねています。
最近ではリモートワークが推進されていますが、デバイスによってデジタル化されたマニュアルが表示対応していなかったり、環境が整理されていなかったり、検索性の悪さから「伝わらないマニュアル」になっていることが浮き彫りになっています。
長年、企業のマニュアル制作をお手伝いしてきた当社が大切にしているのは、「伝わるマニュアル」です。そもそもマニュアルとは、業務の標準を作ることです。業務標準は判断の拠りどころや行動の目安になります。判断の拠りどころや行動の目安とするためには、正確性や確実性が求められます。正確・確実なマニュアルは、書き手の主観を含めず、安全や衛生基準、その他規格などを常に事実、エビデンスに基づいて執筆する必要があります。
当社が掲げる「伝わるマニュアル」の条件は次の5つです。
- 利用者視点で書かれている
- 図・映像で文書の理解を補足する
- 統一感のあるレイアウト、文体、用語にする
- いつでもどこでもすぐに見られる環境を整える
- 常にアップデートされている
①~③は作り方の工夫で、④⑤は運用で解決していくことができます。前者の方が効果が見えやすく、対して後者は対応難易度が高いので、今回は作り方の工夫について説明します。
マニュアルライティング(執筆)の進め方
マニュアルの作り方を知る前に、そもそも貴社のマニュアルの目的を明確にしましょう。マニュアルは現状、仕事ができている人にほかの社員が合わせるための道具であり、判断の物差しや到達目標の指標になります。また新人にとっては、業務の意味の理解や判断の迷いを解消する教科書となり、日々できる仕事が増えて自己成長を実感するのに役立ちます。単に手順を伝えるものではなく、事業承継や持続可能な企業活動を達成することが最終的なゴールであり、目的となるということです。
目的をしっかりと意識したうえでマニュアルを作成していくには業務を一覧化、区分けをして、使われる状況を把握し、部門ごとの特性課題を盛り込んで形にしていきます。闇雲に紙へ落とし込めばいいのではなく、どんな業務があるのか、順を追って噛み砕いていくことが大切です。そうすることで効率を上げつつ、業務の棚卸が可能になります。社内で情報が共有できていれば顧客に対しても素早く正確な情報を提供できるので結果として、顧客満足度を向上していくことが可能になり、企業の成長に結びついていきます。
業務を分解する時は、「どの段階でするべきことなのか?」「どうなったらするべきことなのか?」「どうやってするべきことなのか?」「何をもって完了とするか?」という4つの段階から考えていきましょう。業務フローは一連の流れとして動きますが、「その業務はどんな時にやっているのか」といったところから分析していきます。
4つの段階で分解した業務は
- 「どの段階でするべきことなのか?」⇒作業フロー
- 「どうなったらするべきことなのか?」⇒判断基準
- 「どうやってするべきことなのか?」⇒作業手順
- 「何をもって完了とするか?」⇒合否判定
としてマニュアルに展開していくことができます。
マニュアル作成では、作業手順が一番フォーカスされやすいですが、実はその前後の作業フローや判断基準、合否判定といった大切な段階があることを忘れないでください。
当社では企業様のマニュアルを「ユーザーに理解してもらうマニュアル」という視点で検証し、改善点等をご提案する『マニュアル標準化サービス』や、より具体的なマニュアル改善のポイントを当社の専門スタッフが解説するWebセミナーを順次開催しております。以下にセミナー案内及びサービスの資料を掲載いたしますので、ぜひご覧ください。また、同サービスのご依頼やその他ご質問等については、お気軽に問い合わせ窓口からご連絡いただければと思います。
オンラインセミナーのご案内
株式会社クイックスでは、マニュアル作成についての無料オンラインセミナーを開催しています。
ご都合よろしければぜひご参加ください。
セミナー一覧はこちら
『マニュアル標準化サービス』マニュアル制作のプロに検証・改善してほしいという方へ
クイックスの「業務マニュアル検証・改善サポートサービス」では、現状の業務マニュアル分析から読み手に伝わりやすくするための構造化の案をご提案するサービスをご用意しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
『業務マニュアル検証・改善サポートサービス』(515KB)
マニュアルに関するお問い合わせはこちら
開催中のイベント・セミナー Events / Seminars
マニュアル
オンデマンドセミナー
オンデマンドセミナー